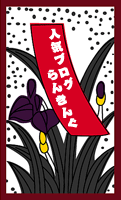子供の頃、祖母宅の蔵に入るのが好きでした。
真っ暗な中、懐中電灯で照らしながら探検すると、とんでもなく古い鎧や法螺貝と共に色々な古銭が出てきました。
残念ながら、今はもう蔵に古銭はありません。
従兄弟が高校~大学生の時、小遣い欲しさに売ってしまった...と聞きました^^;
その従兄弟本人も叔父・叔母、祖母も亡くなり、何年も経ちました。 今、その家には従兄弟の一人息子が住んでいますが、彼ももう40代。 私にとって、かつては、自宅のように馴染みがあった場所ですが、代が替わればよその家。 この家で祖母と過ごした日々は現在の家の主が生まれるずっと昔の話。 叔父や叔母、従兄弟の思い出も全て過ぎ去った遠い過去。 やがて忘却の彼方に消え行くことでしょう。 その前に、ささやかな歴史の欠片として写真の一枚でも残しておこうと思います。

手前の細い道を入れば叔母の家。 昔は入口にムクロ樹の大木があった。
さて、骨董好きな息子宛てに古銭市のDMが届いた為、久しぶりに二人で古銭市に足を運びました。
知識がない私は買わずに見るだけでしたが...
**********
今週のお題「30万円あったら」
もし、臨時で30万円の正当な入金があり、それを絶対に使わねばならないなら、アンティークな金貨を買うのも面白いかもしれません。 もちろん、予算に合うものがあれば...の話ですが。
**********
*:;;;:*:;;;:*<< 目次 >>*:;;;:*:;;;:*
*:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:**:;;;:*:;;;:*
コインショー
訪れたのは天満橋のOMMで開催された大阪コインショー。
この展示会は日本貨幣商協同組合の主催です。
↑ 2023年後半も東京・名古屋・大阪を中心にイベントが催されるようです。
入口で受付を済ませ、セキュリティーチェックもなく、警備員に会釈しながら入場しました。 業種を問わず、日本の展示会はフレンドリーで緊張せずに入場できるのが魅力です。
丁度、セミナーが始まったようで、入口近くのセミナー会場に人があふれていました。
また、コインショーというものの紙幣も沢山出品されているようでした。
そんな中、ちょっと気になったのは「松木」と印字された金貨が複数販売されていた事です。
松木 金貨
なぜ「松木」なのでしょう?
展示販売をされている方に聞いてみましたが、「松木さんという掘り師の名前です。」との事。 つまり、鉱山を任され掘っている責任者の名前、と仰っていました。
「じゃあ、なぜ、掘り師の名前が金貨になるの?」
聞いてみたかったのですが、忙しそうにされていた為、諦めました。
帰宅後、ググってみて行き当たったのが、日本銀行金融研究所のページ。
(↓)
https://www.imes.boj.or.jp/cm/exhibition/2007/mod/07kosyu.pdf
その中に江戸幕府から甲州金製造の独占権を与えられたのが、松木さんであると記載されています。 つまり、松木と表記されているのは幕府が正式に製造を認めた「甲州金」である証明なのでしょう。
投資なのか趣味なのか
息子の話では「今日も帯つきのお札で買っている人がいた」とのこと。 何も知らない私は「すごいね。珍しいんじゃない?」と聞き返したのですが、「いつもいるよ。」との事。
個人でも、目利きができる人は「投資目的」で購入されるかも知れません。
また、業者間の売買もあるでしょう。 出展者の中には外国人らしき人もいらっしゃいますので、自国で仕入れた商品を展示会で販売し、自国で仕入れにくいものを会期中に他社のブースで探すこともあり得ます。 もちろん、国内でも得意分野は各々異なるでしょう。
私のように資金も知恵も限られている個人は感心しながら眺めるだけですが...
それでも少しだけ思うところはあります。
ちょっと気になったのがアンティーク金貨です。
趣味としてのアンティーク金貨
会場を歩いていて小冊子をもらいました。

ページを繰ると「ローマのアウレウス金貨」や中世ヨーロッパの金貨、ラテン通貨同盟の金貨など色々な金貨のことが書かれていました。 歴史を学ぶ上でも面白そうです。
古銭収集には歴史の知識が必要です。
骨董・美術品としての価値で値付けされている金貨を見る中、頭によぎるのが、金としての価値。
株式や外貨同様に市場で刻々と変わる金の値段と骨董品として販売されている金貨の価格は果たして連動しているのだろうか...? 金が暴落すれば、歴史的な価値や美術品としての値打ちはそのままでも、どの程度、値段が変わるのだろうか...?
美しい金貨を眺めながら下世話な事を考えてしまいました。
そして、「もう少し歴史の勉強をしてから出直そう。」 そう思ったのでした。
カード決済も可能と言いつつ、こういった展示会では、まだまだ、現金での売買が中心です。
展示会の警備
会場入り口で感じたのは警備に威圧感がない事。 とはいえ、価値の高いものを展示し、現金でヤリトリをしている為、来場者に気づかれぬよう目を光らせていると想像します。 その上で、表面上はフレンドリーで温かみのある雰囲気を出しているのは立派だと思いました。
特に手荷物検査がないのは日本的だな、と感じました。 会場で現金を扱う限り、海外ならば武装した警備員が入口で怖い顔で睨みを利かせるはずです。 もちろん、日本でも大きなカバンを持って居れば止められるとは思いますが、入場時も退場時も厳しい表情を向けられることは全くありませんでした。
そこで、比較してしまうのが、他国の展示会警備。
(コロナ禍以降、海外に出ていないので、ちょっと古い情報です。 状況が変わっていたらゴメンナサイ。)
中国の展示会警備
金品を扱う展示会でなくとも、中国で開催される見本市では小さなバッグに至るまで手荷物はすべてX線を通し、空港のようなセキュリティーゲートを抜けねばなりません。 (交通機関もそうです。 上海で地下鉄に乗る際、必ず、改札の手前で荷物検査を受ける為、ラッシュアワーは大変です。)
余談ですが、セキュリティーが厳しい割に中国の展示会の警備はビックリするほど甘い部分もあります。

靴を脱いでいるのは、せめてもの気遣いか??
セキュリティーが厳しい中国。 しかし、こういった事(↑)は警備員に叱られないのが腑に落ちません。^^;
他にも、厳しいセキュリティーの中、どうやって入ってくるのか分かりませんが、弁当をはじめ色々な物品の販売業者らしき姿を見かけます。 一番驚いた経験は、開場前に「立入禁止」のテープをくぐり、競合他社の担当者がこちらのブースに入り込み、勝手に機器の電源を入れていた事です。 その時はさすがに見つけた知人が競合相手に強弁にクレームを入れ、私も警備を管理する主催者に文句を聞いて貰いましたが、中国語が不得手な為、主催者がこの件を重要な事と捉えてくれているのか判断できず歯がゆい気分でした。
警備ひとつとっても、国によって(または業種によって)問題視される部分が異なるのでしょう。 国内外で色々な業種の展示会を見に行くと面白い発見があります。
**************
今日も最後まで、お付き合い頂き有難うございました。 m_ _m
金と言えば思い出すのが All that glitters is not gold. (光っているものがすべて金であるとは限らない。)という言葉。
シェイクスピアのヴェニスの商人に登場する名言なんですね... 当初、私は、それを知らず、この曲(↓)の歌詞のおかげで All that glitters is gold. (光ってるものは全部、金!)と覚えてしまいました。
この曲については過去記事をどうぞ...
楽天やamazonでお買い得品をお探しの方は、どうぞ、下記を併せてご覧・ご利用ください。
ブログランキングに参加してみました。
記事がちょっぴり気になった方、ポチってくれたら嬉しいです。



 復刻版 古銭コレクション 日本の大判・小判・金貨 [6.甲州大判(金)](単品)](https://m.media-amazon.com/images/I/51pwS4TQFGL._SL500_.jpg)