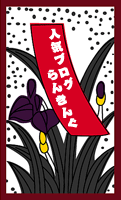毎年7月下旬にせともの市が催されるようです。
その神社は火防陶器神社(ひぶせとうきじんじゃ)と呼ばれ、坐摩神社(いかすりじんじゃ)の末社です。
火防陶器神社

元々、火防陶器神社は西区靭南通1丁目にあったものの、市電敷設の道路拡張のため、明治時代に現在の場所に移された、との事。
坐摩神社の境内に西向きに建立されています。
阪神高速の下につづく参道
中央大通りから阪神高速の高架沿いに南下した所で神社の案内らしきものを見つけました。
よく見ると「火防陶器神社」と書いてあります。



案内に沿って高架下を進むと、鳥居が見えてきます。


鳥居の右の燈篭の横に坐摩神社と書かれています。
鳥居の左の燈篭横には火防陶器神社と書かれています。
ここは坐摩神社の西鳥居。
東鳥居が正面玄関のようです。
(坐摩神社の本殿及び神社会館は東鳥居をくぐって正面です。)
火防陶器神社の本殿は西鳥居をくぐり左側に鎮座しております。 (稲荷神社と左右に並んでいます。)


火除の神様として陶器商人に崇拝されている火防陶器神社。 明治40年(1907年)に移設される前は西区靱南通1丁目で愛宕山将軍地蔵を祀っていたと伝えられています。 当時、筋違橋(すじちがいばし)から四つ橋の西側まで南北に陶器問屋街が広がり約200軒が軒を連ねていた、との事。 (丁度、大阪メトロの肥後橋駅の南側から南に二駅、四ツ橋駅までのエリアです。) そして陶器神社はその守護神でした。 現在、飾られている陶器の灯籠は、前の神社から移されたものです。
筋違橋や四つ橋など、大阪の地名には「橋」が沢山出てきます。 かつては水都と呼ばれていた大阪です。 川に沿って発展した商業の街だったのでしょう。
とはいえ、街の風景を眺めてみても、かつて、この辺りに川が流れていた事はなかなかイメージできません。
上方落語寄席発祥の地
火防陶器神社の本殿の横を通り抜け、さらに進むと、広々とした坐摩神社に辿り着きます。 そして、その手前に「上方落語寄席発祥の地」という碑があります。

「あれっ? 上方落語の発祥ってここだっけ?」
少し疑問が湧きました。
「上方落語の発祥の地は生國魂神社」と誰かに聞いたことがあります。
碑をまじまじと眺めると「上方落語寄席発祥の地」と書いてあります。
坐摩神社は1798年(寛政10年)に初代桂文治が常打ちの寄席の看板を初めてあげた場所。
それまで大道芸に近い芸能だった落語を室内の高座で演ずる興行形式に改めた、と言われています。
なお、火防陶器神社の陶器市は7月21日、22日、23日の3日間開催されます。
詳しくは大阪府陶磁器商業協同組合のホームページをどうぞ。。。
**************
今日も最後まで、お付き合い頂き有難うございました。 m_ _m
この界隈についての過去記事はコチラ ↓

当ブログの商品紹介、お店やホテル紹介にはアフィリエイトサービスを利用しております。
その他、楽天でお買い得品をお探しの方は、どうぞ、下記を併せてご覧・ご利用ください。
更新頻度は低いのですが別ブログに日常の中で撮った写真やデザイン画をアップしています。 宜しければお暇な時にご訪問下さい。。。
ブログランキングに参加してみました。
記事がちょっぴり気になった方、ポチってくれたら嬉しいです。